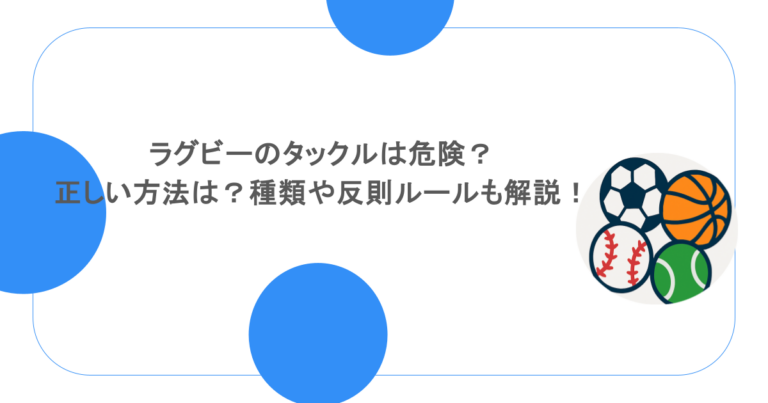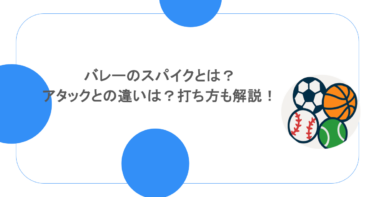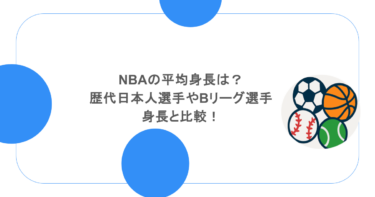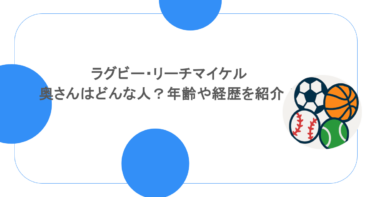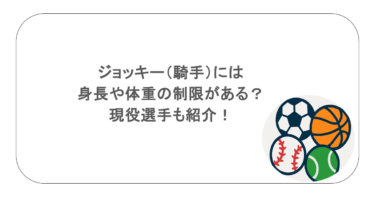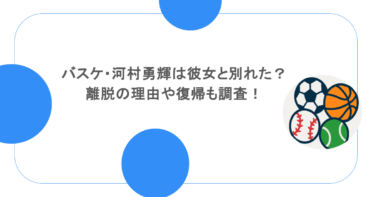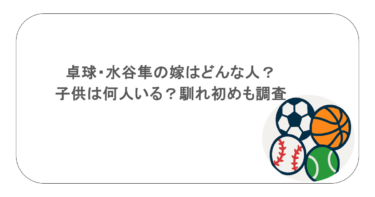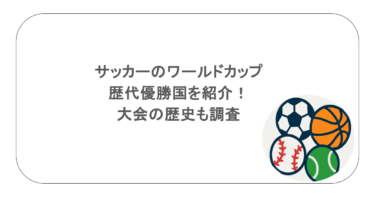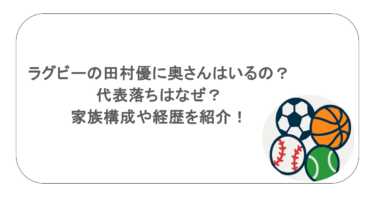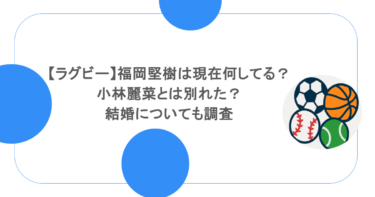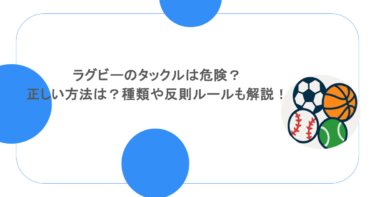様々なスポーツの中でもフィジカルコンタクトが激しいスポーツとして知られているラグビーですが、怪我をしないためには正しい方法を知っておく必要がありますね。また、ファウルっぽく見えるタックルですが、どういったプレーがラグビーの反則に該当するのでしょうか。
そこで今回は、ラグビーのタックルは危険なのか、正しい方法や種類、反則ルールについて解説していきたいと思います。
ラグビーのタックルは危険?正しい方法を解説!
プレーの激しさなどからラグビーのタックルは危険に見えてしまいますが、正しい方法を身に付けておくことで、怪我のリスクを減らすことが出来ます。
まず、タックルを行うときはしっかりと視線を上げ、ボールを持っている選手を見て、低く安定した姿勢をすることが重要です。また、タックルする選手は胸骨よりも下のエリアを目掛けて行うようにし、頭は相手選手の横につけるようにしましょう。
こうすることで頭部へのダメージなどを最小限に抑えることができ、怪我のリスクを減らすことが出来ます。
ラグビーのタックルの種類はいくつある?
一見、1つのパターンしかないように見えるラグビーのタックルですが、実はいくつか種類があり、状況に応じて使い分けることが重要です。それでは、ラグビーのタックルの種類について、特徴や注意点などを交えながら紹介していきたいと思います。
フロントタックル
フロントタックルは名前からも分かるとおり、ボールを持っている選手に対して真正面からぶつかっていくタックルで、進行方向とは反対に倒します。フロントタックルは低い姿勢から両腕を使って相手選手の足を掴むことで上手く倒すことが可能です。
ただ、フロントタックルは正面からぶつかっていくため、衝撃が凄く、身体能力だけではなく、タイミングや相手に向かっていく精神力の強さも求められます。
サイドタックル
サイドタックルは相手選手の側面からぶつかっていくタックルで、選手が避けようとするため試合中に多く見られるプレーの1つです。サイドタックルを行うときは肩を軸にして行うことで相手を倒すことができます。
スマザータックル
ラグビーのタックルは低い姿勢から行うことが基本となっていますが、スマザータックルは相手選手のパスを防いだり、ボールを奪うことを目的にしているため上半身に向かって行います。スマザータックルは倒すことよりもボールを奪うことなどが目的なので、相手の腕の動きを封じるようにしましょう。
チョップタックル
チョップタックルは相手選手の腰より低い位置に向かって行うタックルで、主に体格差があるときに使われます。上手く決まれば、周囲にいる選手がボールを奪うこともできますが、倒される間際にパスを出されてしまうリスクもあるのが特徴です。
リアタックル
リアタックルは後ろから相手選手に飛びつき、足に腕などをかけて転ばせる方法です。リアタックルは重量差があっても行えるタックルですが、相手選手をしっかりと掴んでいないと、プレーが続行されてしまうので注意しましょう。
ラグビーのタックルの反則ルールも紹介
ラグビーのタックルは相手を止められれば、何をしても良いという訳ではありません。選手生命に影響を与えないようにラグビーのタックルにも反則ルールが設定されているので、しっかりと確認していきましょう。
ハイタックル
相手選手の胸骨(肩)よりも上にタックルすることは大怪我を負ってしまう危険性があるため、反則とされており、ペナルティキックやシンビンと呼ばれる一時的な退場などのペナルティが科される可能性があります。
ノーボールタックル
ラグビーではボールを持っている選手にしかタックルすることは許されておらず、ノーボールタックルは反則行為です。もし、ノーボールタックルをした場合には、相手チームにペナルティキックが与えられます。
レイトチャージ
レイトチャージは相手選手がパス、キックなどをした後に遅れてチャージすることを指します。レイトチャージをした場合はノーボールタックルと同じようにペナルティキックが与えられます。
アーリータックル
ボールを持っていない選手、パスなどを受ける前にタックルした場合はアーリータックルが適用されます。アーリータックルは悪質と判断された場合、一発退場となってしまうこともあるので注意しましょう。
スティファームタックル
スティファームタックルとは、相手選手に体を密着させて倒すのではなく、腕を伸ばし振り回すようにするプレーのことを指します。場合によってはシンビンや一発退場の可能性があるので、気を付けるようにしましょう。
まとめ
今回はラグビーのタックルは危険なのか、正しい方法や種類、反則ルールについて解説してきました。
ラグビーのタックルは正しい方法を身に付けておくことで怪我のリスクを抑えることが出来ます。また、反則ルールになっているタックルは相手選手を怪我させるリスクが高いので、しっかりと覚え、行わないようにしましょう。